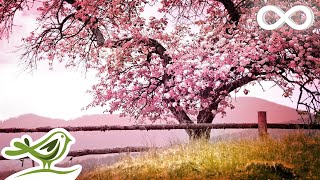【希少公開】ピアノレス版 ラプソディ・イン・ブルー RHAPSODY IN BLUE Pianoless Ver. サウスウィンド吹奏楽団 SOUTHWIND/Rare Public Video
HTML-код
- Опубликовано: 6 фев 2025
- ラプソディ・イン・ブルー
初演時のオーケストレーション、F.グローフェによる
ピアノレス・吹奏楽編成 1938年版
作曲:ジョージ・ガーシュウィン 編曲:ファーディ・グローフェ
【希少公開】
RHAPSODY IN BLUE
~Pianoless, Wind Ensemble Ver. 1938~
by the arranger of the first performance 1924
Music by George Gershwin Arr.by Ferde Grofé
/Rare Public Video
サウスウィンド吹奏楽団 第30回定期演奏会
2024年10月6日 西宮市市民会館 ベイコム・アミティホール
指揮:今井克己 撮影:孝洋屋
SOUTHWIND Wind Symphony
Conducted by Katsumi Imai
Nishinomiya City, Hyogo, Japan
【音楽の背景】
1924年1月、すでに有名になり多忙のジョージ・ガーシュウィンが、兄のアイラ・ガーシュウィン(おもに作詞を担当)と息抜きのために訪れたビリヤード場で、翌月の実験的演奏会ために、「(キング・オブ・ジャズの)ポール・ホワイトマンがガーシュウィンに曲を発注した」という新聞記事を目にした事が作曲の発端です。実は全く「寝耳に水」の彼は、翌日、抗議のためホワイトマンに電話をかけるも、この記事はガーシュウィンを呼びつけるために作った偽記事ということで、「新聞記事になってしまったから作ってくれ」と押し切られてしまい、ガーシュウィンは約2週間で一気にピアノ2台での総譜のみを書き上げました(バンド譜については後述)。そして翌2月、ガーシュウィン自身のピアノ独奏とポール・ホワイトマン・バンドによって、ニューヨーク・エオリアンホールで「新しい音楽の試み」とのコンサートにて歴史的初演がなされました。
【楽曲のもう一人の重要人物、グローフェ】
ファーディ・グローフェ(Ferde Grofé 1892〜1972)はニューヨークでクラシック音楽家の両親の下に生まれ、ピアノやヴァイオリンを母から習得します。7歳のころ父親を亡くしますが、その後母親に連れられドイツのライプツィヒへ移住し、ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、作曲を学び、また、バリトンホルン、コルネット、ドラムなど幅広い楽器に堪能となります。このことがのちに管弦楽作曲に役立つこととなりました。14歳のときには家を出て仕事を転々としながら15歳からはダンスバンドに参加するなどのバンド活動を続けていました。1909年からロサンゼルス交響楽団にヴィオラ奏者として10年間務め、その後28歳の頃、1920年からポール・ホワイトマン・バンドのチーフ・アレンジャーに抜擢され何百もの曲に関わり、活躍します。
グローフェは、このような立場でガーシュウィンによるこの楽曲のオーケストレーションを任されることになります。(ちなみに、ピアノ独奏部のカデンツァは、初演当日も未完であったため、本番において、ガーシュウィン自身の即興アドリブとなりました。)
この後、1932年までホワイトマンの元でアレンジャーを務めますが、その間、1926年にグローフェ最初の主要な組曲「ミシシッピ組曲」(昔、TV番組「アメリカ横断ウルトラクイズ」に一部が使用されていましたので、グローフェやこの組曲を知らなくても、曲を聞いたことがあ
る方々は実は多いと思います。)がホワイトマン管弦楽団の演奏で初演され、作曲家としても認められ、また1931年にはグローフェの最も有名な作品「グランド・キャニオン組曲」がホワイトマン管弦楽団の演奏で初演されたことなどもあって、1932年、独立し、その後も指揮者、作曲家、編曲家として活躍し、1972年に80歳にてこの世を去りました。ちなみに、この「ラプソディ・イン・ブルー」について権利関係でガーシュウィン側と争うことも生じましたが、最終的には和解しています。
【楽曲について】
題名のラプソディは「狂詩曲」という、叙事詩や民族音楽的な性格の音楽を表しています。作曲当初は「アメリカン・ラプソディ」としていたのですが、兄アイラの助言で「ラプソディ・イン・ブルー」となりました。ブルーは色名というより、ブルース、ジャズの「ブルーノート」(後述)の
意味合いが強いものです。また、このジャズ分野のみでなく、前述のように、ガーシュウィンのルーツ、ユダヤ民族音楽の「クレツマー・スケール」(後述)の影響や、当時のジャズ誕生前夜の「ラグタイム」、そして南米キューバ発祥のラテン音楽「ソン」などの影響も感じられ、そ
れゆえに、20世紀最大のメロディー・メーカーによって、クラシック、ジャズ、ユダヤ音楽、ラテン音楽など、移民大国の音を混ぜ込んだ、オリジナルの「アメリカの民族音楽」が誕生したと言えるでしょう。
〇数々の魅力的旋律
この音楽の旋律の一部を挙げると、冒頭のクラリネット独奏による印象的なグリッサンド から続く、TVドラマ「のだめカンタービレ」でも印象的に使用された旋律 がこの音楽全体にわたり奏でられます。この旋律は下降系のため少し哀愁を持った性格を持ち、また何か懐かしげな雰囲気もあ
ります。これを少し専門的に掘り下げます。この主題は、彼自身のルーツ、ユダヤ民族
音楽の「クレツマー・スケール」(ドから始まる音階の場合、レ♭、ミ、ファ、ソ、ラ♭、シ
♭)と、アメリカで生まれた「ブルーノート」(ドから始まる音階の場合、ミ♭、ソ♭、
シ♭)を巧みに組み合わせて生み出されています。また独奏クラリネットに続くホルン・ソリによる、やはり「クレツマー・スケール」と「ブルーノート・スケール」(他のスケール音含む)の組み合わせによる旋律 もこのあと何度も登場します。また途中、リズミカルな打
楽器や中低音楽器に乗ったトランペット等による軽やかな旋律は、「この音楽の曲想が生まれたのはボストン行きの汽車の中で、リズミカルな機械音に刺激されて、突如として曲の構想が最初から最後まで思い浮かび、楽譜としてすら見えた」と作曲者自身が残していますので、その雰囲
気を表しているのかもしれません。さらには「ラグタイム」的な高音木管によるシンコペーションのリズムをバックにした低音楽器などで奏でられる旋律や、この曲の中、もっとも甘く美しい、やはり「のだめカンタービレ」での印象が心に残る旋律など、豊かなメロディーが散りばめられています。
【今回のピアノレス版に関して 】
ジャズ・バンドとピアノ独奏による1924年初演での成功によって2年後グローフェによりピアノ独奏+管弦楽編成版が作られ、さらにこのグローフェ稿を基本としたフランク・キャンベル=ワトソンによって1942年、ピアノ独奏+管弦楽編成版が製作され、現在、クラシックやジャズの名ピアニスト独奏とオーケストラ編成で取り上げられるものの多くはこのワトソン版です。
ここからは、個人的な考えをもとに述べます。ワトソン版の少し前、1938年、グローフェによって、今回のピアノレスによる吹奏楽版と、同じくピアノレスによる管弦楽版が発表されます。いずれも調べる限り、一般的に手に入る録音等が全く見つかりませんし、現在取り上げられることも皆無です。しかしながら、このピアノレス版は重要な意味を持っているのではないかと推測します。
なぜならガーシュウィンは1937 年、わずか 38 歳にてこの世を去ってしまい、このピアノレス版は、その翌年に、初演時の共同制作者といえるグローフェによって発表されたものです。この事から、ピアノレスというコンセプトは次のように想像できるのではないでしょうか。『ガーシュウィンがこの世にいなくなってしまった』との嘆きを持った深い思いを、『ピアノを失ったサウンド』で示す、との考えではないかと想像しています。
現在、この歴史的にも重要なピアノレス版を録音、ライブに限らず聴く機会が皆無なのは、残念で仕方ありません。
“About this piano-less version”
The success of the first performance by jazz band and piano solo in 1924 led to Grofe's version for piano solo and orchestra two years later, and Frank Campbell-Watson produced the version for piano solo and orchestra in 1942 based on Grofe's manuscript. Today, most of the classical and jazz pieces that are performed by famous pianists and orchestras are based on Watson's version.
Here is my personal opinion on this piece. Shortly before Watson's version, in 1938, Grofe published two versions, this time for brass band without piano and for orchestra, also without piano. As far as I can find, there are no recordings of either of these versions available to the general public, and none of them are currently being performed. However, I suspect that this pianoless version has an important meaning.
Gershwin died in 1937 at the age of 38, and this piano-less version was published the following year by Grofe, who was a co-producer of the first performance. The concept of the pianoless version can be imagined as follows: “Gershwin was not alive at the time of his death, but he was still alive at the time of his death. I imagine that the idea behind the pianoless version was to show the deep lamentation of “Gershwin's absence from the world” through the “sound of the missing piano.
It is a pity that there are currently no opportunities to hear this historically important pianoless version, whether recorded or live.